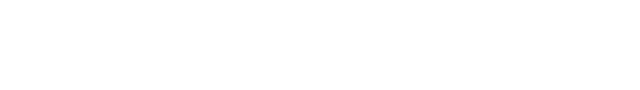頚部脊柱管狭窄症 頚椎症性脊髄症
頚椎症性脊髄症とは、頚椎の脊柱管の狭い状態に椎間板狭小と後方膨隆、後方骨棘などの加齢性の変化、さらに頚椎前後屈での不安定性や外傷などが加って脊髄障害を引き起こす疾患の総称です。
各種画像検査で脊柱管狭窄および脊髄圧迫所見を認め、脊髄責任病変の高位と圧迫病変部位が一致することが重要となります。
<病態>
病態としては大きく二つに分けられます。
- 静的圧迫因子
1、頚椎の発育性脊柱管狭窄
一般的12mm以下が絶対的な脊柱管狭窄と考えられています。頚椎の発育性脊柱管狭窄は重要な頚椎症性脊髄症の素因となり得ます。
2 、頚椎症性変化
加齢に伴う椎間板の変性や膨隆、椎体の後方骨棘、黄色靱帯の肥厚や膨隆などにより脊柱管は狭くなります。さらに発育性狭窄を伴うと脊髄が圧迫を受けやすくなり頚椎症性脊髄症が発生しやすくなります。
- 動的圧迫因子
頚椎の後屈時における黄色靱帯の脊柱管内へのたくれ込みや前後屈時における椎体の不安定性によるすべりが頚椎症性脊髄症を発症する重要な因子です。加齢により弾性を失った黄色靱帯は頚椎後屈に伴いゆるみ、後方から脊髄圧迫を引き起こします。
<疫学>
頚椎症性脊髄症は男性の発症が女性の約2倍以上で50歳以降に発症することが多いです。発育性脊柱管狭窄を伴う場合、30-40歳代で発症することもあります。
<症状、診察>
病期や重症度により症状は異なりますが主に脊髄中心部が障害されるタイプと脊髄が横断的に障害されるタイプがあります。前者は上肢の運動感覚症状を主症状とし、後者は上肢のみならず下肢の運動感覚症状を伴うことが多いです。
手指あるいは足の痺れや知覚異常で発症することが多く、症状が進行するに従って、手の巧緻運動障害や歩行困難を自覚します。箸が使いにくい、ボタンが留めにくい、書字が困難などであり、下肢症状は速く歩けない、階段の下りが怖いという訴えを聞くことが多いです。
手指の伸展と屈曲を繰り返し片手ずつ10秒間行い、その回数を数える10秒テストが20回以下で、伸展が遅くなる場合は頸髄症を疑う所見となります。
横断的に障害されるタイプでは、障害高位以下の知覚障害、腱反射異常、
Hoffman徴候やBabinski徴候、筋力低下や排尿障害などが出現します。これらを総合的に判断することである程度の高位診断は可能となります。
<検査>
基本的には腰部脊柱管狭窄症の項目でも述べたように、レントゲンの後にMRIを行うことで確定診断に至ることがほとんどです。
1、単純レントゲン像
頚椎正面および中間位側面像の2方向および最大前後屈の側面像が基本となります。前後屈機能撮影を行うことで不安定性の評価が可能となります。
2、MRI
頚椎症性脊髄症の診断に欠かせない画像診断です。しかしながら骨棘か軟部組織かなどの圧迫因子自体の鑑別には不向きであり単純レントゲンや単純CTなどとの併用が望まれます。T2強調画像ではくも膜下腔は白く写し出され、頚椎症性脊髄症ではくも膜下腔の消失が明らかとなり脊髄実質の圧迫状況も確認できます。
さらにMRIを行うことで椎間板ヘルニアや脊髄腫瘍の除外に役立ちます。
3、脊髄造影検査
脊髄造影およびCTM(脊髄造影後CT)は基本的には手術を前提とした症例に行うことが多く入院が必要となります。特に脊髄腔造影は椎体の動きや黄色靱帯の突出の診断に有利です。CTMはより詳細に圧迫の形態が把握でき脊髄の萎縮を含めた形態の診断に役立ちます。
特に手術を予定する症例については依然として必須の検査となります。
<診断>
画像上硬膜管や脊髄の圧迫が認められても全てが必ずしも症状の原因となっているわけでないため、神経学的所見との対比が極めて重要となります。
画像所見から説明のつかない症状がある場合には脊髄変性疾患や頸髄の炎症、頭蓋内病変、末梢神経病変など頸髄以外の疾患の可能性を念頭に置くことが大切です。必要に応じ電気生理学的検査、髄液検査なども行います。
<治療>
①保存治療
感覚障害が主で、運動障害が軽微な例や脊髄症状を呈しても日常生活に支障のない場合は経過観察や保存治療の対象となることが多いです。一般的に保存治療に含まれるものとしては、薬物療法、装具療法、頚椎牽引療法、日常生活における頚部肢位のアドバイスなどが挙げられます。
頚椎装具や非ステロイド性抗炎症薬、生活指導の組み合わせによる軽症例の頚髄症に対する保存療法の成績は2年間のフォローでは手術群と差がないことが示されています。しかし痙性麻痺出現から1年以上経つ症例や重症例は手術成績は不良であり漫然とした保存療法を重ねるべきではなく脊髄症の進行を見落とさないことが重要となります。
特に、頚椎症患者は転倒などによる頚椎の急激な過伸展で症状が急激に悪化することもあるため、生活指導が必要となります。
②手術療法
保存治療に抵抗性のある症例をはじめ、一般的に以下のような状態が手術適応とされています。
手指の巧緻運動障害、歩行障害、排尿障害などが生じ、脊髄障害が明瞭で日常生活や就労に支障が生じた場合は手術適応となります。特に脊髄障害が進行性の場合には早期手術が必要です。